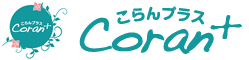男女で異なる体の変化:更年期の基礎知識
更年期は、誰もが迎える体の転換期です。しかし、男女でホルモンの変化の仕方や、それに伴う症状の出方には大きな違いがあります。まずは、ご自身の体の変化がどのようなメカニズムで起こっているのかを知ることが、更年期を乗り切るための最初のステップです。
I. 女性の更年期:ホルモンが急降下する「転換期」
一般的に女性の更年期は、閉経を挟む前後約10年間(一般的に45歳~55歳頃)に訪れます。
女性の卵胞は37、38歳を過ぎたころから急速に減少し、50歳でほぼ消滅すると言われています。このように、加齢にともなう卵胞の数の減少や卵巣の機能低下によって、閉経がもたらされます。卵胞が急速に減少する時期はプレ更年期、そして、消滅する時期は更年期に当たる時期とされています。
1. 変化のメカニズム
卵胞の減少は卵巣の機能低下を伴い、女性ホルモンの分泌の減少につながります。
更年期は女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)が急激に減少します。この急激なホルモン量の変化に体がついていけず、脳の自律神経中枢が混乱し、全身にさまざまな不調が現れます。
2. 「プレ更年期」とは? 東洋医学の視点
最近では、30代後半から、ホルモン検査ではホルモンの減少が更年期に該当しないにもかかわらず、更年期に似たイライラや疲労感などの症状を敏感に感じ始める女性が増えています。これは「プレ更年期」と呼ばれます。
東洋医学では、この時期の不安定な状態は、ホルモン分泌を調整し、血(栄養)を貯蔵する「肝(かん)」の働きが、過度なストレスや疲労で乱れ始め、「肝血(かんけつ)」が不足し始めたことによると考えます。
3. 主な症状と東洋医学の視点
更年期の症状は多岐にわたりますが、特に「腎(じん)」、「心(しん)」、「肝(かん)」の乱れとして捉えます。
| 症状 | 東洋医学的な関連 |
| ホットフラッシュ、発汗 | 自律神経の混乱による熱の異常な上衝(のぼせ) |
| イライラ、不安、不眠 | ストレスを司る「肝」の気の滞りや、精神を司る「心」の乱れ |
| 乾燥、抜け毛、目の疲れ | 栄養分である「肝血」の不足。髪が細くなり、皮膚や目の潤いが失われます。 |
| 疲労感、体力低下 | 生命力の根源である「腎」の衰えで老化の始まり |
II. 男性の更年期:ゆるやかに進む「活力の低下」
男性の更年期は、40代以降で徐々に現れ始め、女性ほど明確な終わりがありません。50~60代で最も多く発症した後は、長期的に症状が持続するのが特徴です。これはLOH症候群とも呼ばれます。
1. 変化のメカニズム
男性ホルモンであるテストステロンは、女性のエストロゲンのように急激に減少するわけではなく、ゆるやかに低下します。しかし、仕事のストレス、過労、睡眠不足といった要因が加わることで、テストステロンの分泌が急ブレーキを踏み、不調が顕在化します。女性よりも長期化する傾向があるため、いち早く東洋医学を取り入れることで早期にQOLの向上につながります。
2. 主な症状と東洋医学の視点
症状は身体的なものより、精神的なものや性機能の低下が目立ちます。東洋医学では「腎」の衰えに加え、ストレスによる「肝(かん)」の乱れが重要になります。
| 症状 | 東洋医学的な関連 |
| やる気が出ない、抑うつ | 「腎」の衰えによる活力の低下、「肝」の気の滞り |
| ED、性欲減退 | 「腎」の機能低下と下半身の血流不足 |
| 内臓脂肪増加、疲労感 | 代謝を司る機能の低下や、エネルギー(気)の不足 |
| イライラ、集中力低下 | ストレスによる「肝」の機能の乱れ |
III. 鍼灸と漢方ができること
更年期はホルモン補充療法が一般的ですが、体質改善を並行することで、治療効果を高めたり、薬に頼りすぎない体づくりが可能です。
東洋医学は、ホルモン数値を直接操作するのではなく、乱れた自律神経や低下した「腎」の働き、そして不足した「肝血」を補うことで、体自身が持つバランスを取り戻す力をサポートします。
当店では、男女それぞれの症状と体質を細かく分析し、オーダーメイドの鍼灸と漢方で、つらい更年期を乗り切って、前向きに過ごすためのヒントをご提案しています。ぜひお気軽にご相談ください。